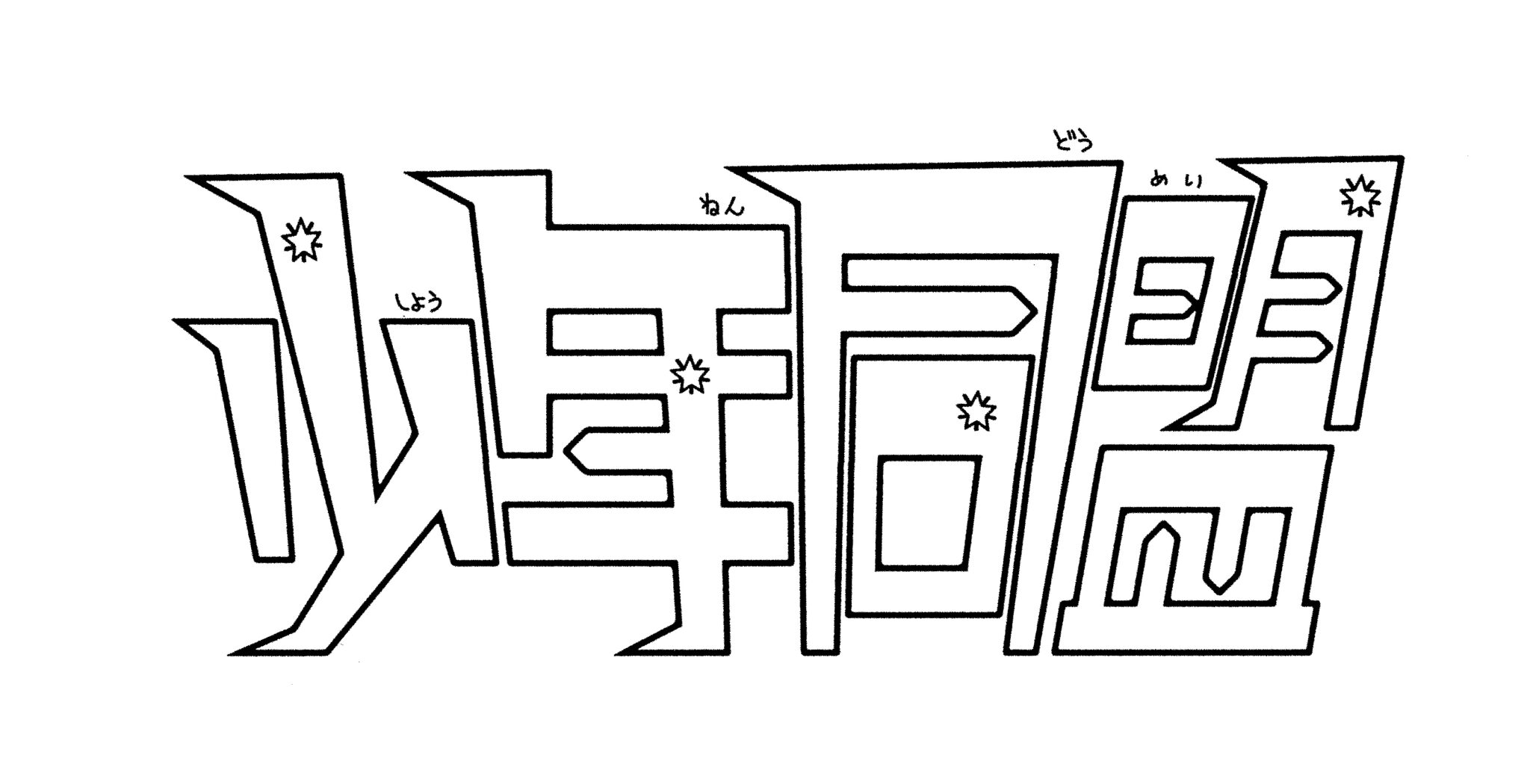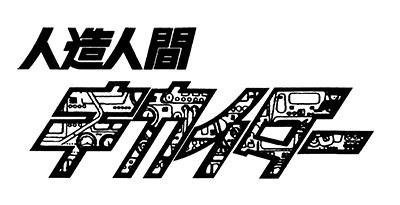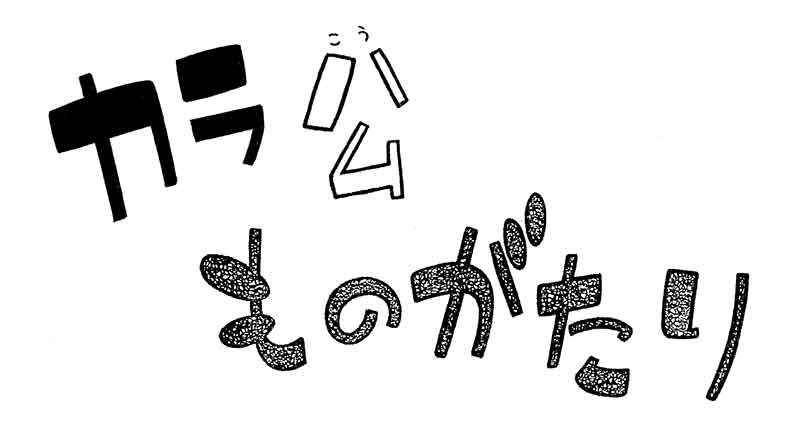丈 プロフィール
俳優として、15歳から初舞台を踏み、梅沢武生、梅沢富美男、浜木綿子、藤田まこと、左とん平、渡瀬恒彦など、多くの先輩俳優に師事し、影響を受け修行も積む。現在、シリアスも演じられる個性派の喜劇俳優として認められている。他に、三遊亭圓窓に師事し、「三流亭舞大」という名前を貰い、高座経験も持つ落語の腕前はセミプロと評されるほど。その落語も披露し、連作短編集の構成で演じる 自身のひとり芝居は、その構成の妙と数名を演じ分ける 演者としての幅の広さに、高い評価を得ている。
20歳で旗揚げし、途中10年間の充電期間はあるものの、プロデュースユニット JOE Companyの演劇活動は、ライフワークとして現在も継続中である。
演劇プロデューサーとしての評価もさることながら、脚本、演出をし創作する その作品は、SF、ファンタジー、コメディ、ミステリー、サスペンス、ラブストーリーとジャンルにとらわれない、自身にしか描けない作風。
何処にでもある日常に、非日常が絡むユニークな発想に引き込まれ、喜劇性豊かなストーリーに笑い、人間が持つ普遍的なテーマに感動し、緻密に練りこまれた構成と大胆な演出で表現される独自の世界に熱中するフリークが急増中。創作者としての評価も、作品を発表する度に登りつめている。
龍神沼

萬画好きの方の中で、これほど有名な短編読み切り作品はないと思います。中には、この作品を石森章太郎の最高傑作と評する方がいるほど、非常にクオリティの高い作品です。これを、1961年に描いたというのですから驚きです。
青いマン華鏡 後編

以前、初めて青年誌を立ち上げた元小学館の伝説の編集長だった小西湧之助さんのお話をさせて頂いたと思うのですが、石森章太郎という萬画家が描く作品は大人っぽ過ぎて、所謂、その業界の大人たちには認められていたけど、読者の少年少女達には受けなくて、ヒット作になかなか恵まれない、玄人受けするコアな萬画家であったと。
青いマン華鏡 前編

数多くの作品を描き、長編の傑作も数知れず、短編作品も当然の如く、心に残るものが多数存在致します。小説で例えるなら、私小説的な作品も、作者の作品郡をみると、決して少なくありません。そのような作品を並べてみると、やはり、故郷での出来事や、上京後のトキワ壮時代の話が多いような気がいたします。
鉄面探偵ゲン 第2回
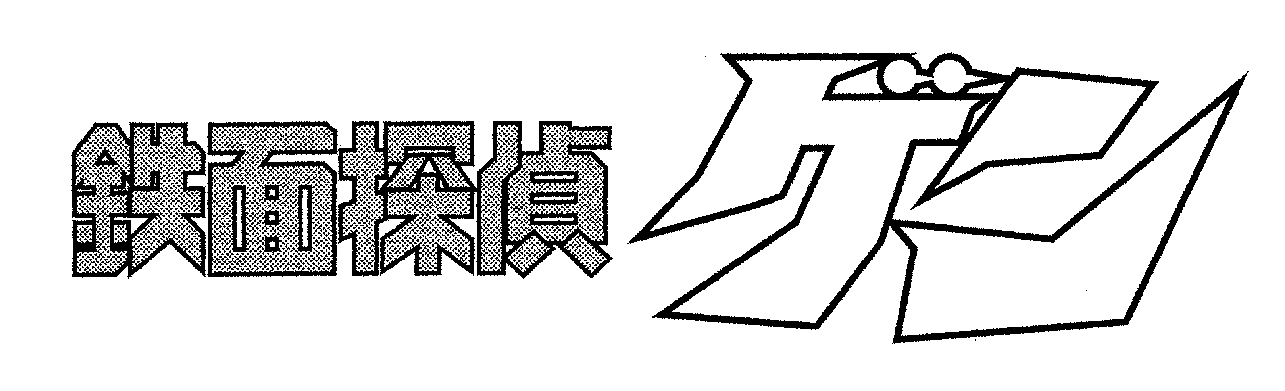
この作品は、その後連載作品としてスタートしますが、一貫して、その世界観はブレることなく、本格推理マンガというジャンルを快走します。石森作品と言えば、SFであったり、ヒーロー作品を思い描く方が多いと思います。
鉄面探偵ゲン 第1回
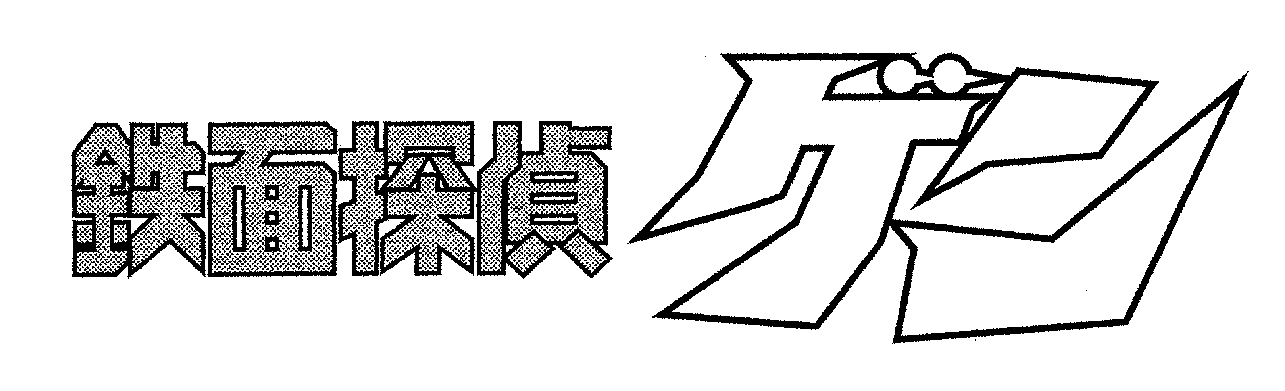
これは、『酔いどれ探偵鉄面クロス』の続編にあたる作品です。設定は全く一緒ですし、主人公がタコの足を加えているのも一緒。ただ違うのは、クロスがヒーローもの作品だったのが、こちらは本格推理マンガになっている事です。
酔いどれ探偵鉄面クロス 第2回
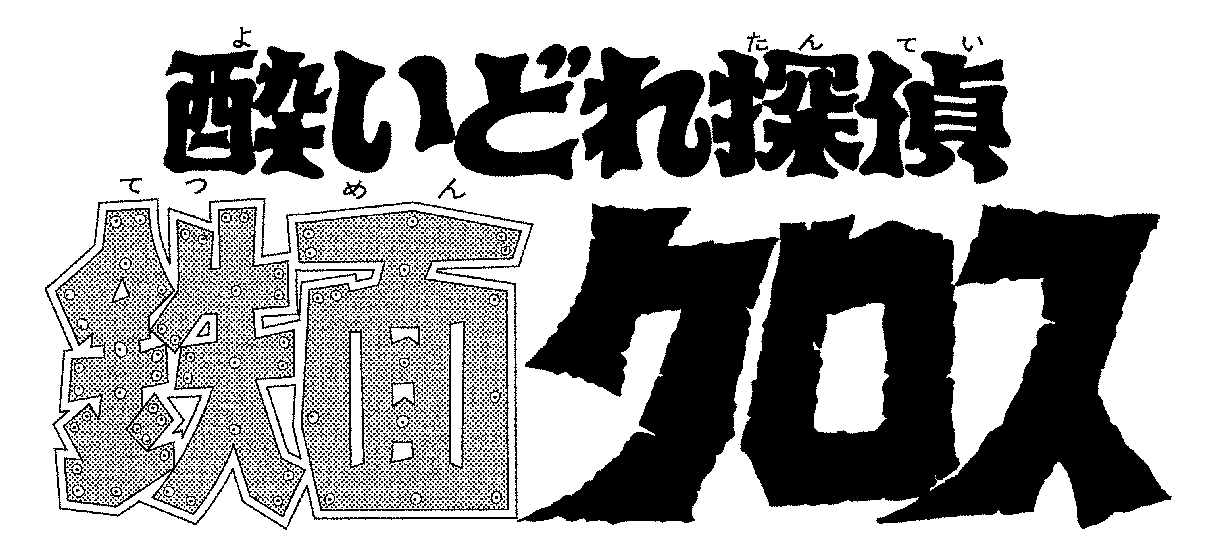
僕の中で、酔っぱらいのヒーローと言えば、水島新司先生の『あぶさん』を真っ先に思い出します。近年は超人的な活躍をする人になりましたが、最初は、一振りにかける代打屋という設定が渋くて、そこに人生が見えました。
酔いどれ探偵鉄面クロス 第1回
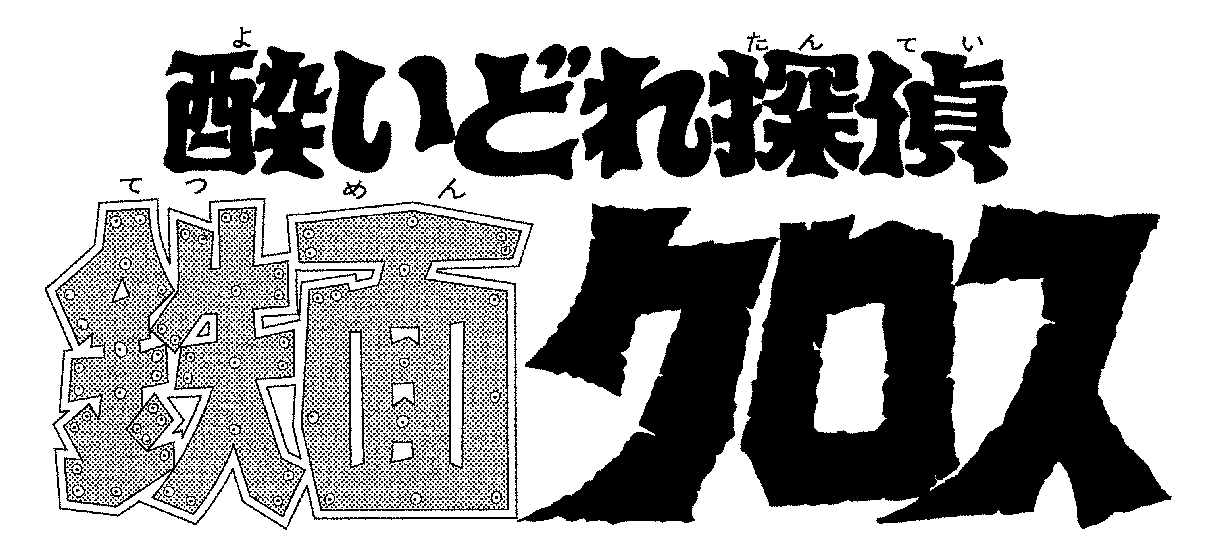
かつて、僕がレギュラー出演していたドラマで、『スケバン刑事』という作品がありました。マンガが原作ではありますが、石森作品ではありませんよ。和田慎二先生の作品。
石森章太郎読切劇場 鋏 はさみ 第4回
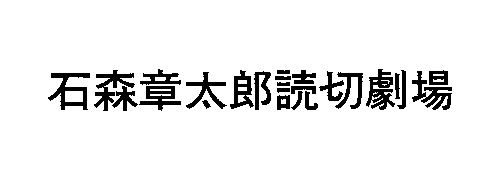
単行本の紹介記事に、この作品を“衝撃作”と綴ってありました。 それは、この作品がメタフィクション、いや、本当に実話だったかもしれないからです。
石森章太郎読切劇場 海の部屋 第3回
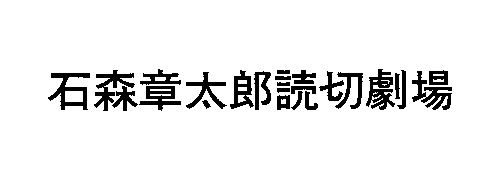
1969年から70年まで、プレイコミックで掲載された読切作品集。 大人の雑誌なわけですから、当然のことながら、大人向けの題材のストーリーが多いのは無理もありません。 さすがに小学校では無かったですが、中学くらいかなぁ。
石森章太郎読切劇場 カラーンコローン・遠い日の紅 第2回
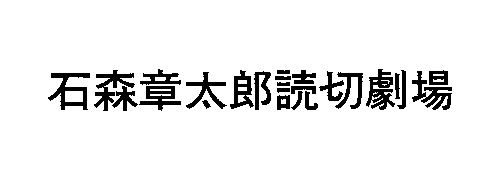
石森にはお弟子さんが沢山います。そう言うと謙虚な本人は、照れくさそうに“弟子”という言葉をやんわり否定すると思いますが、古くは永井豪先生は始め、すがやみつる先生、ひおあきら先生など、アシスタントから巣立っていかれた先生方は多数存在致します。
石森章太郎読切劇場 だまし絵 第1回
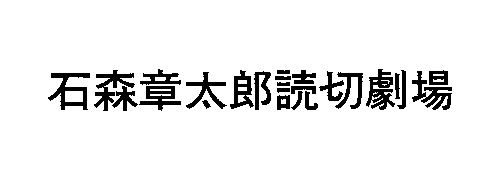
一つのテーマで描く短編集と違って、好き勝手に自分の描きたいテーマを縛られることなく、読切で発表できる場はさぞかし楽しかったのではないでしょうか。
水色の星
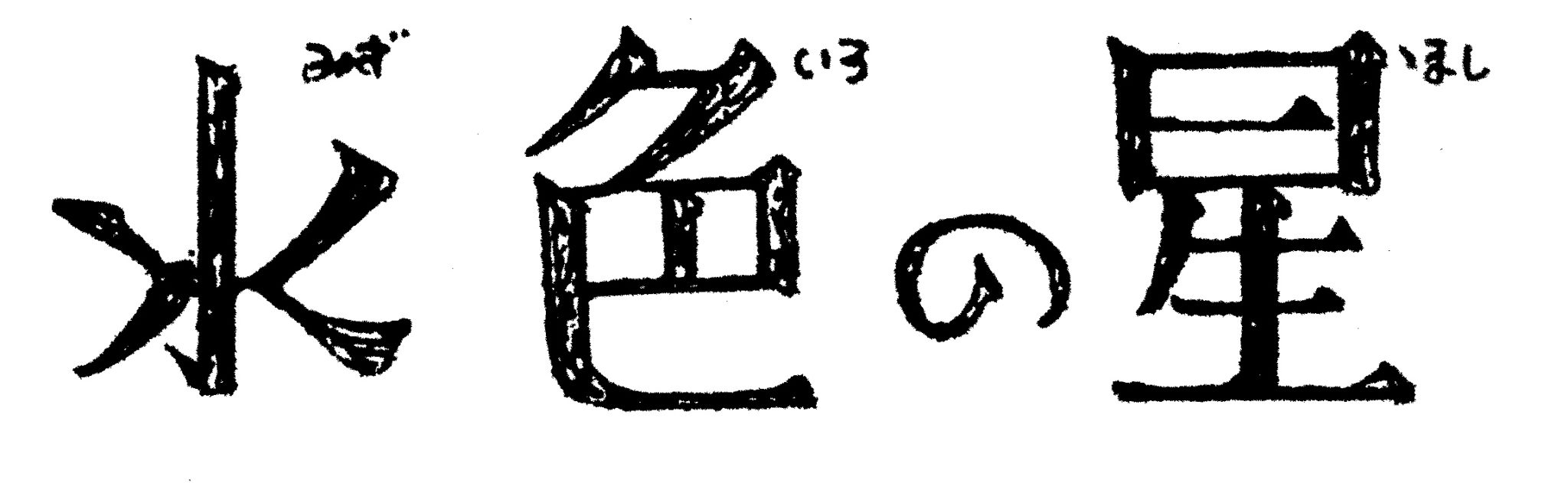
有名な作品にも触れたいと思いますが、どちらかというと、余り知られていない作品の方を紹介したいという気持ちも強く持っております。特に短編作品は、よほど石森作品が好きな人以外は、全く触れる機会がないかと思いますので、今回も、そういう作品を紹介したいと思います。
星の子チョビン 第3回

海外資本の二大娯楽施設と言えば、「ディズニーランド」と「ユニバーサルスタジオジャパン」。近年は、USJはディズニーを超えるほど活況を呈していますが、開業して直ぐに足を運んだ時は、ディズニーランドを超えるのは難しいと直感しました。
星の子チョビン 第2回

前回は、幼児ものの作品に関わらず、父から託された「星のしずく」を自分の星に持ち帰り、悪党と闘う設定が、いかにもヒーロー作品を創り続けた、石森らしい設定だと書きました。
星の子チョビン 第1回

僕にも二人の男の子がいて、育児にもなるべく積極的に参加をして育ててきました。子供たちと接して、初めて子供の目線で何を好むのかを理解出来たりします。この世に生まれて、まず最初に子供たちが好きになるキャラクターは、恐らく「アンパンマン」です。
星の伝説アガルタ 後編

石森のアシスタント希望の黒木シュンと出逢った橘レミの周辺で不可思議な現象が起こり、それをきっかけで秋田の山奥に向かう。謎の薬を飲み続けるシュン、秋田に残る遺跡や現象、その謎に迫ってゆくと驚愕の事実に出合う。簡単なあらすじは、こんな感じです。作者は古代遺跡や文明、UFOや超常現象などに昔から興味を持ち、ロマンを感じておりました。だから、作者が描くSF作品は、それが色濃く出る題材が多いのです。
星の伝説アガルタ 前編

この作品は実に印象深い作品なのです。僕が小学生の時でした。直ぐご近所に丁度中学生のお姉さんがおりまして、「アガルタ」を連載している週刊少女コミックを愛読しておりました。ある日、僕のところまで来て、「あの後、どうなったか教えて」と聞いてきました。ある週のラストシーンの続きがどうしても知りたくて、翌週まで待てなかったようです。
夜は千の目をもっている 第2話
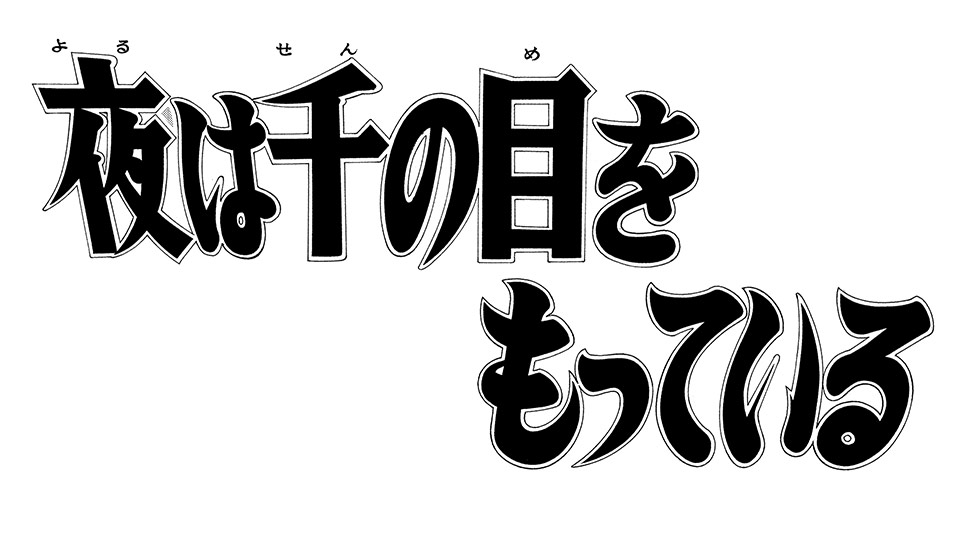
自分は昭和41年生まれ。当然戦争を知らない世代です。ある時、ふと自分が生まれた年は、戦後20年しか経っていない事に改めて気付き、驚いたことがあります。
夜は千の目をもっている 第1話
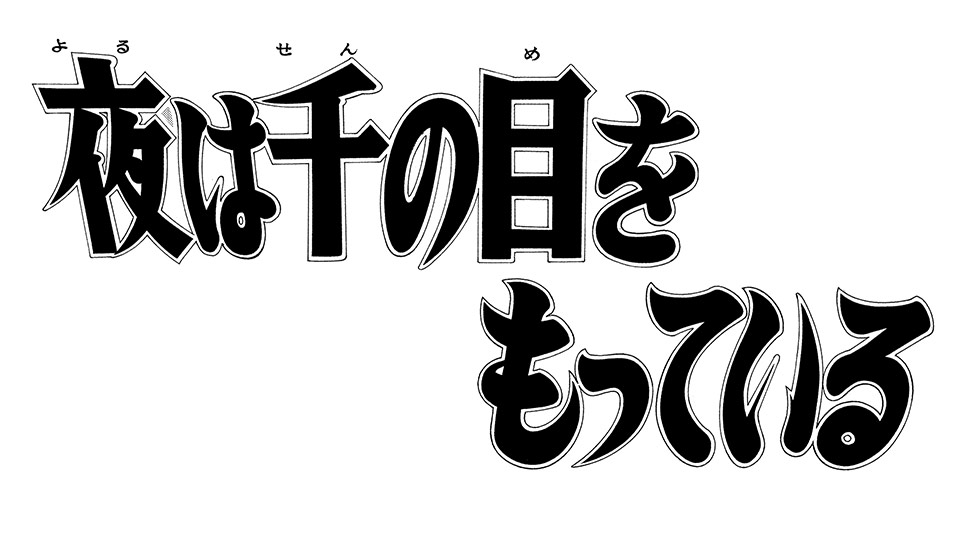
萬画に限らず、小説でもそうですが、雑誌に掲載する場合、連載を続けていく長編作品と、短編の読み切り作品の2つの形態がございます。今回は、そのうちの読み切り作品にスポット当てたいと思います。
変身忍者嵐

役者も演技が歳を追うごとに変わっていくように、萬画家もそのタッチが変化していくようです。ちばてつや先生が、あるインタビューで「あの時描いた矢吹丈を、現在書けと言われても、全く同じタッチでは書けない」と言っておりました。
写楽 前編
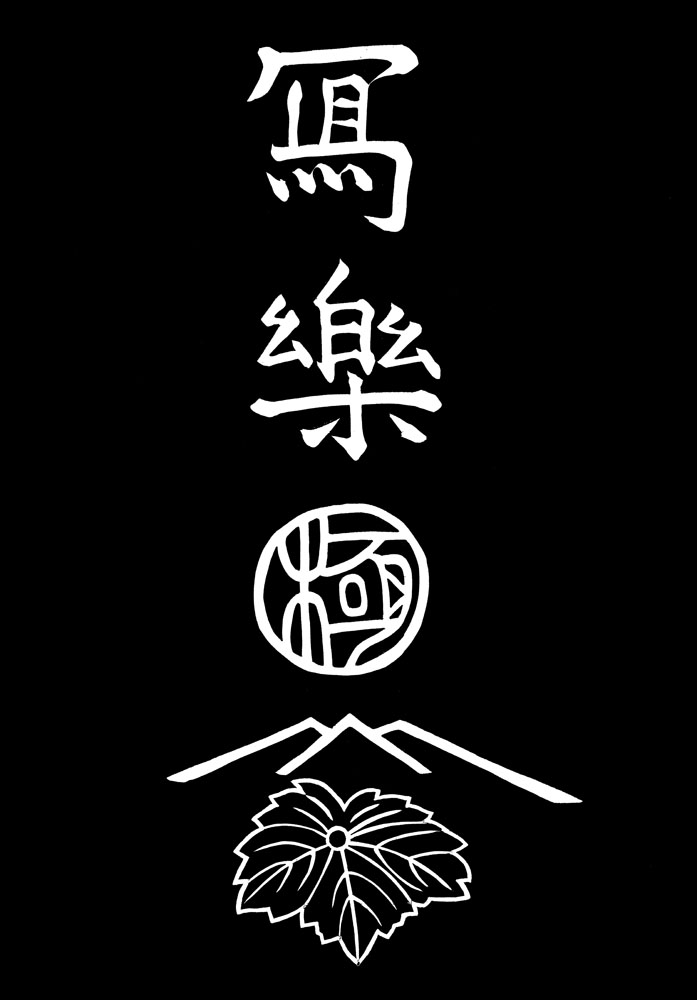
僕も何十と言う単位で戯曲を創作しておりますが、自分が好きな作品の一つに「ほろほろ」という、唯一の時代劇作品があります。しかし、もっと正確に言うと、現代と江戸時代を舞台にリンクしながら物語が進むので、完全な時代劇ではありません。むしろ例えるなら、ファンタジー作品です。
八百八町表裏 化粧師 後編

今までにない時代劇を描こうとして始まった、、、と勝手に推測するこの「化粧師」。 設定の新しさを始めとして、この作品には、多くの試みを感じることが出来ます。
八百八町表裏 化粧師 前編

子供の頃は見向きもしなかったジャンルも、大人になると味わい深く楽しめるようになるものです。 そのうちの一つに、「時代劇」というジャンルの作品がございます。
佐武と市捕り物控・狂い犬
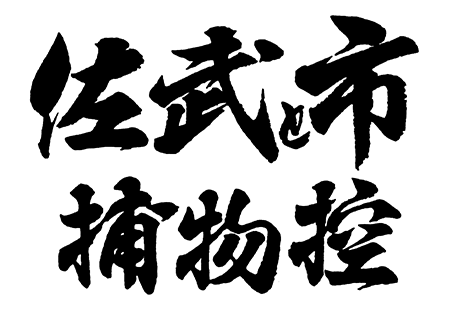
小学館の石森担当だった小西湧之助さんという編集の方がいらっしゃいます。
毎年正月には必ず家に訪れ、石森とは何時間も深くお酒を交わし合う仲です。
最後の入院の時、お見舞いに訪れて下さいまして、管に巻かれた石森の寝顔に向かって、「いろいろ、あったね」と一言、言葉を置いていかれました。
二級天使 後編
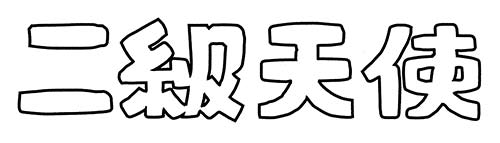
当時の萬画家は、手塚先生も含め、ディズニー作品に影響を受けている方が多く、石森もその一人。キャラクターやタッチが、まさにそう。そして、ウオルトディズニーの実験性も同様に色濃く影響を受けているでしょう。
二級天使 前編
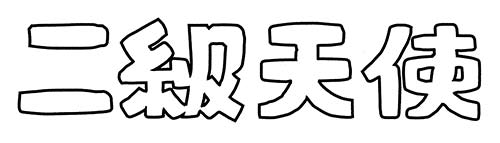
よく僕は石森にこう言われました。「才能は、1パーセントにすぎない、その99パーセントは努力なんだ」僕の胸には、幾つもの言葉が刻まれ、それを大切にしています。特にこれは、自分の人生観にも反映するくらい、影響力のある言葉でした。そんな事を想いながら、作者のデビュー作を久々に開いてみました。
ロボット刑事 後編
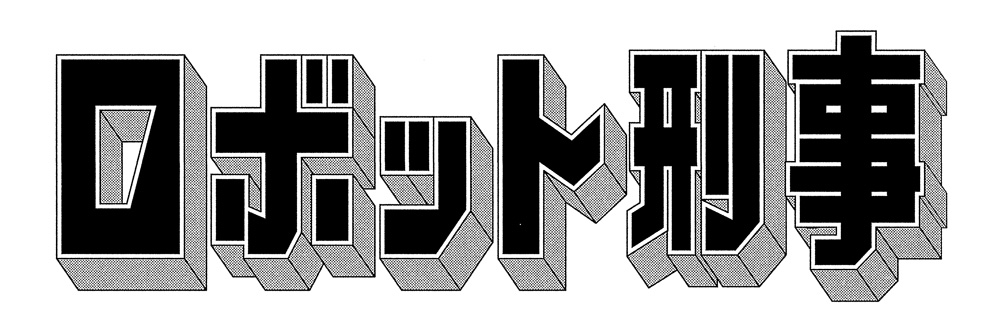
変身をしないヒーローがコンセプトで始まった企画だったそうです。この作品のストーリー自体は、犯罪ロボットレンタル株式会社が敵として存在していますが、テレビ版では描けない事を描いています。
リュウの道 第3回
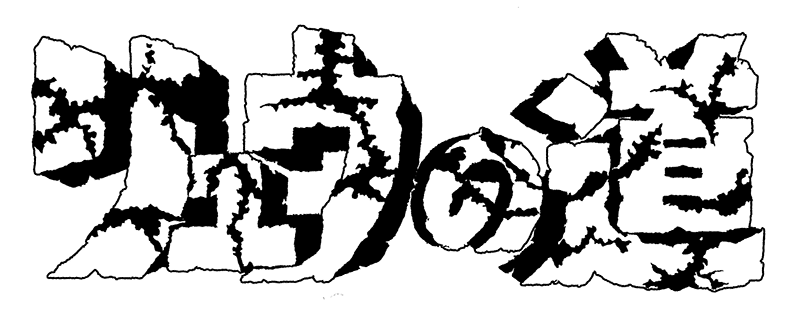
少年マガジンで連載が始まった当時、それまでマンガは少年が読むものでしたが、その概念が壊れ始めた時期でもありました。それは、ビッグコミックという大人が読める青年誌が登場したからです。
リュウの道 第4回
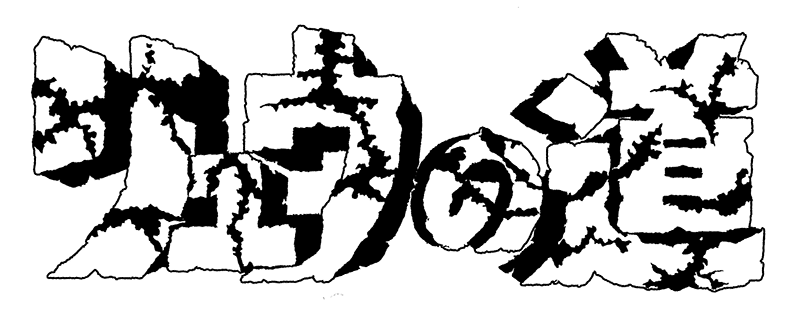
核戦争後の地球に、化け物のような生き物が多数登場します。それは、核の放射能によって突然変異した人間たちや動物。目が三つあったり、乳房が多数あったり、焼け爛れたような容姿だったり…。
マンガ家入門 後編

だいたい、石森より1つか2つ世代前のマンガ家の人たちは、この本はバイブルだというくらい、ここを通ってマンガ家を目指したと聞きます。ミュージシャンや小説家やコピーライターとか、クリエイティブな仕事をしている人たちも、一時マンガ家を目指していたと聞くことが多いのです。
マンガ家入門 前編

誰でしたっけねぇ…確か、石森のお弟子だったか、他のマンガ家の方だったか…、いや、全くマンガとは無縁の方だったか…、とにかく複数の方に言われたんですよ。「この本で、みんな勘違いした」(笑)「先生は本当に罪な人だ」と、もちろん笑いながらですよ。文字だけ追っていくと、とても酷い言葉に聞こえますが、皆さん、一様に笑顔で僕に伝えます。
ファンタジーワールドジュン 後編
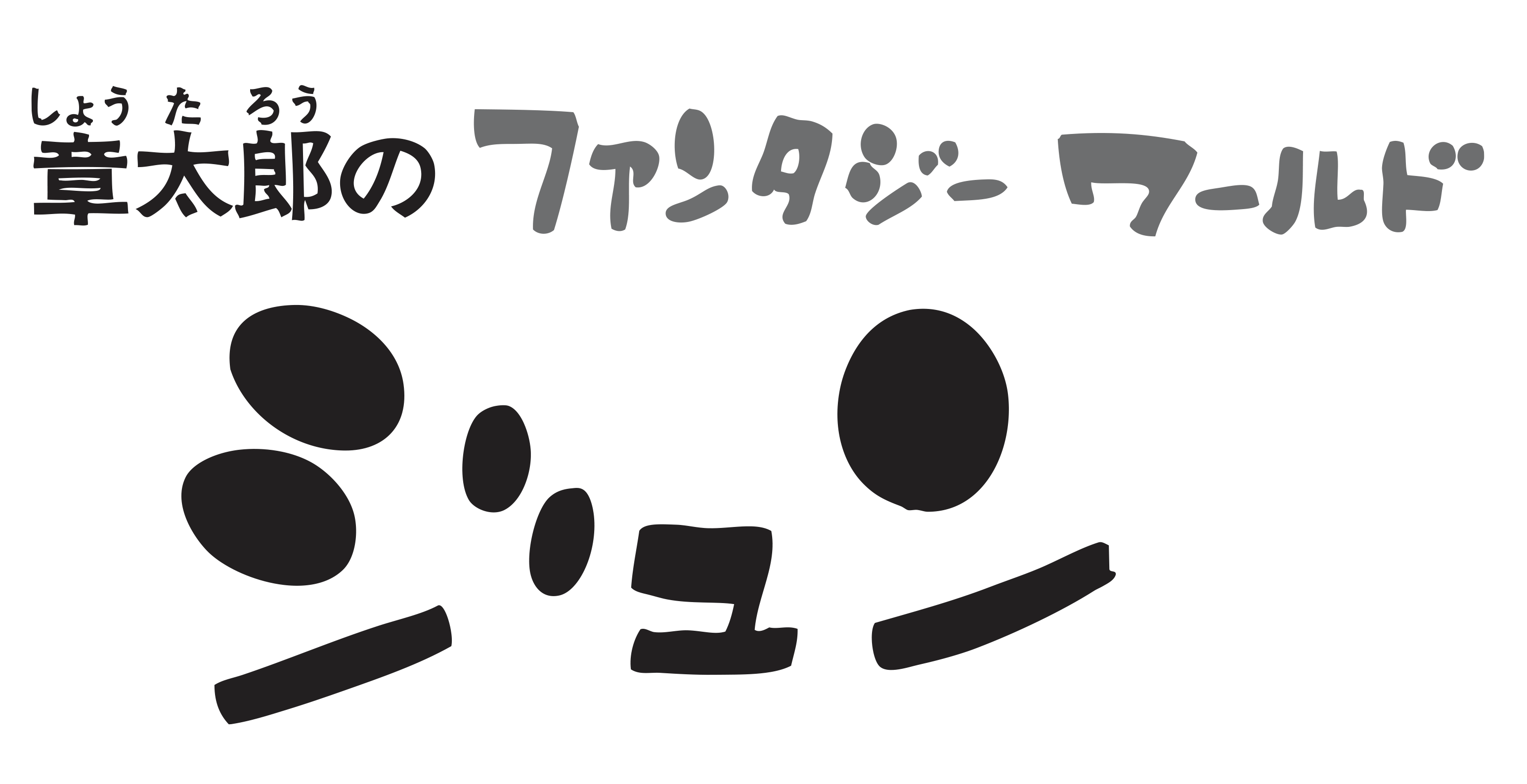
絵だけで、詩を書いてみたい、というコンセプトだったと聞きます。セリフは一切なく、1コマ1コマ、イメージで繋ぎ合わせていく。これほど、評価の難しい作品、いや、言葉で評価を語るような事をしてはいけない作品もありません。
トキワ荘物語 後編
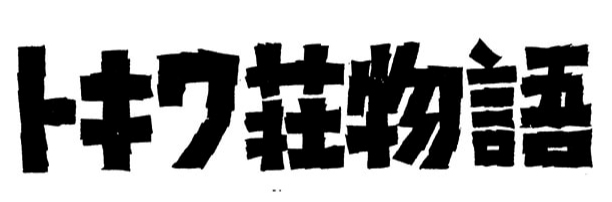
この作品を発表した雑誌の記憶は定かではないのですが、要するに、トキワ荘に所縁のあるマンガ家の皆様がリレーでトキワ荘の思い出を綴る、 読切連載のような形式だったかと思います。
トキワ荘物語 前編
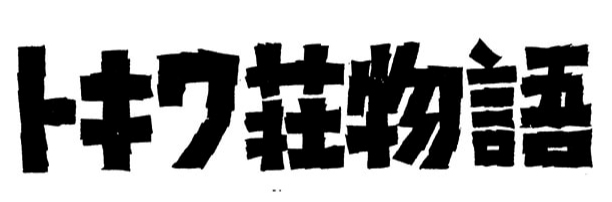
マンガ好きな方には、最も有名なアパート名でしょう。マンガに精通していなくても、この名前を一度は耳にしたことがあるかと思います。 手塚先生がこのアパートで仕事をしていたので、編集の方がマンガ家の卵たちが田舎から上京する度に此処を紹介した事から、 若手マンガ家達が集い暮らすようになった処。
トキワ荘のチャルメラ 後編

前回は、石森特性ラーメンの思い出をお話ししたら止まらなくなり、ページ数全て使ってしまいました(笑)前回お伝えした、インスタントラーメンのブレンド使用の作り方が、「トキワ荘のチャルメラ」という短編作品にも載せてあります。
トキワ荘のチャルメラ 前編

やっぱり環境って、とても影響力のあるものですね。プロ野球の好きなチームがジャイアンツなのも、趣味が映画鑑賞と読書なのも、全て影響を受けるからだと思うのです。
サイボーグ009 父と子編
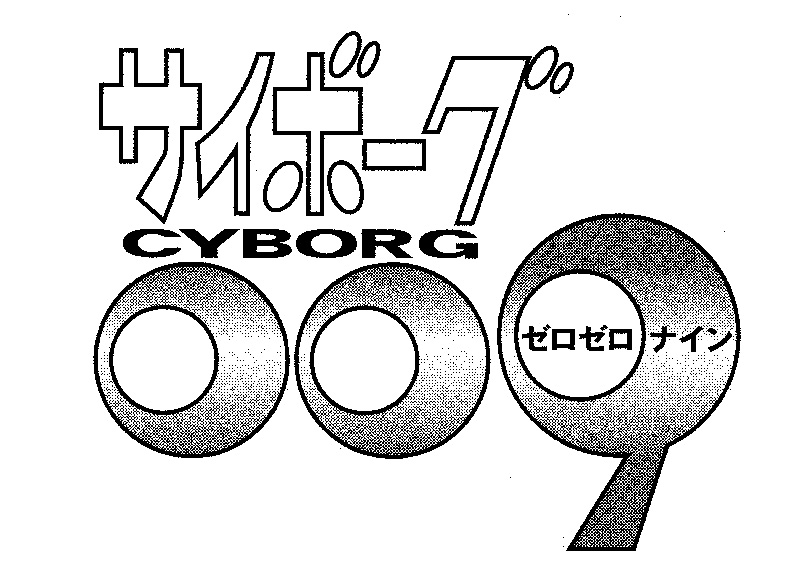
子供の頃はどうしても、サイボーグ戦士の中でも、ジェットやハインリヒのようなカッコいいキャラクターに目が行きがちですが、この歳になってくると、007グレートブリテンのような人間に、味わいを感じてしまいます。
サイボーグ009 まぼろしの犬 クビクロ編
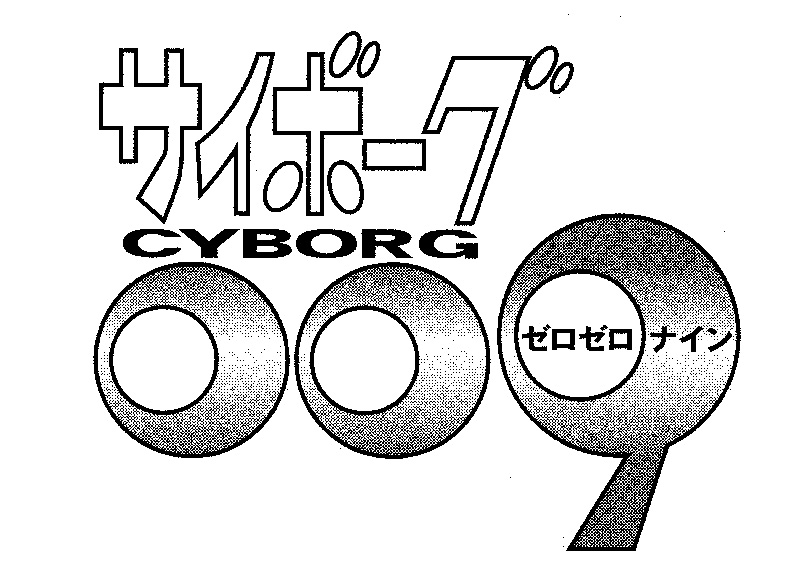
役者の世界では、“動物と子供には敵わない”という言葉があります。どんなに名優が頑張っても、動物か子供が登場したら、全部食われてしまうという意味ですー
サイボーグ009 ベトナム編 後編
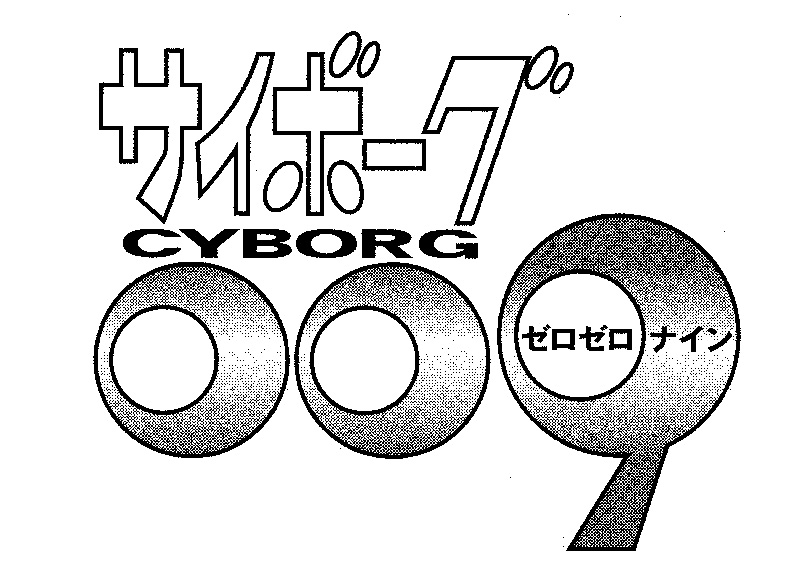
このベトナム編のプロローグでは、人類の歴史は、闘争の歴史だと説いています。人々が争うのは本能なのか、文明進歩のためのエネルギーなのか、必要悪なのかと投げかけて始まるのです。それは、この作品を書いた東西冷戦時も、現代も何ら変わることはない、と僕は思います。
サイボーグ009 ベトナム編 前編
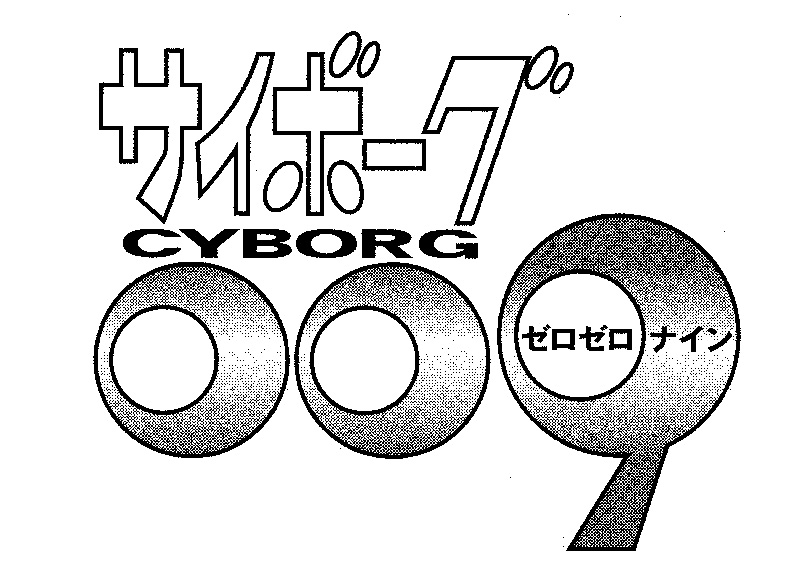
作品をエッセー風に解説して欲しいと依頼を受けまして、こうして書いているのですが、せっかくなら人に余り知られていない作品をご紹介したいと思っておりました。しかし、いきなりのビックタイトル(笑)ただ今回は、ベトナム編に限定させて頂きます。この辺が、ちょいとコアですが(笑)
サイボーグ009 神々との闘い編 前編
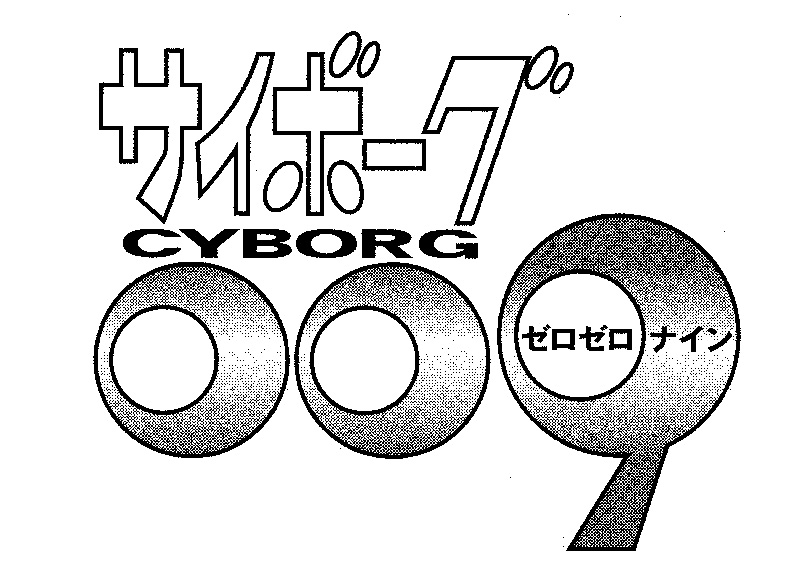
「月刊COM」で、『ジュン』の後に連載した作品です。『ジュン』の事を知った後に、この作品に触れると、その系譜に頷きます。それは、作家性を重んじて、前衛的な実験が許された雑誌に、サイボーグ009という作品を書いたら、きっとこういう表現方法になるのかもれないな、という納得です。
ちゃんちきガッパ 後編
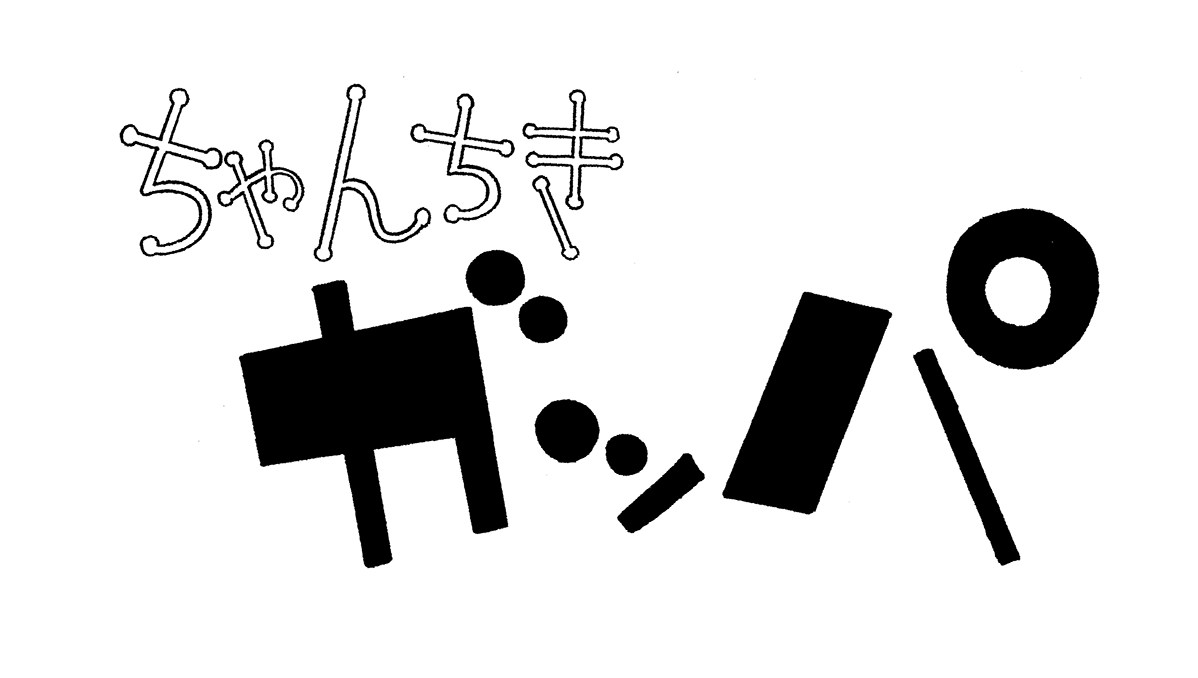
転校生の主人公が、学生帽で黒マント、足元は下駄。昔ながらの出で立ちで、僕の中で学生帽が似合うマンガキャラクターは、「ドカベン」岩鬼と、このちゃんちきガッパが双璧です。「チャンチキおけさ」をよく口ずさむことから、ちゃんちきガッパと呼ばれるようになったようです。
さるとびエッちゃん 後編
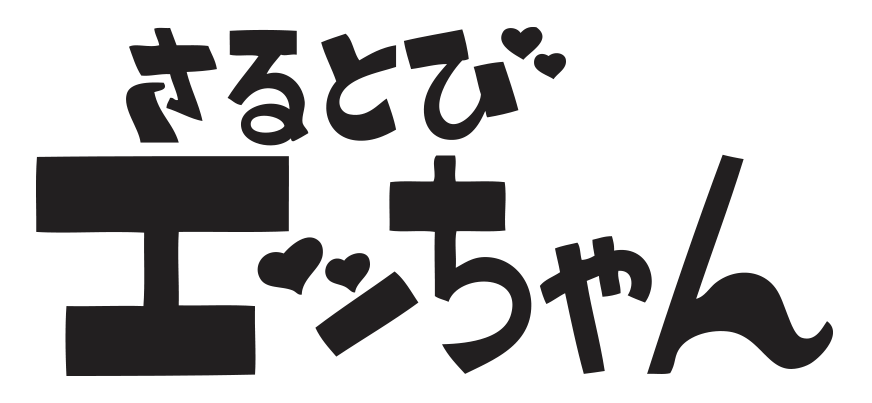
雑誌なのか、テレビのインタビューか、しかも何方が仰ったコメントか定かではありませんが、ベテランのマンガ家の方が、「ギャグマンガを長く続けることは難しい」と仰っていたことを思い出しました。
さるとびエッちゃん 前編
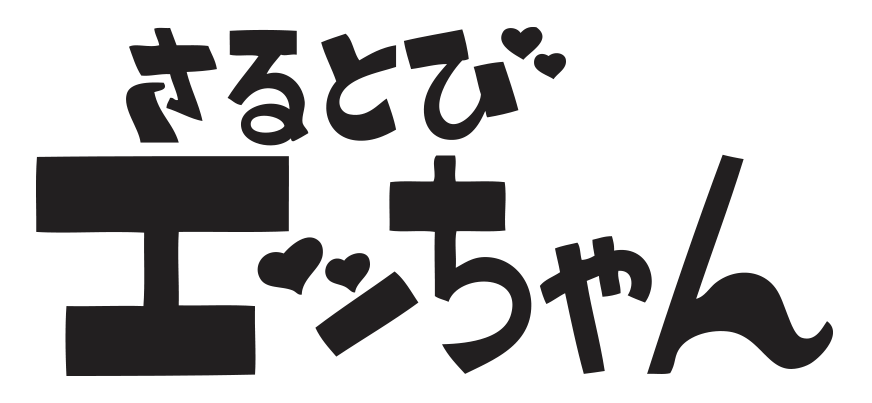
この作品、週刊マーガレットの創刊号で、連載が始まりました。雑誌と共に、エッちゃんも産声を上げました。
創刊する少女マンガ誌にギャグマンガを描こうとする事は、とても勇気のいることだと思います。
やはりギャグマンガと言えば、少年誌が定番ですから。
でも、“実験無くして、進化無し”、何事にも挑戦する作者ならではのチャレンジだったと思います。
その挑戦が生んだ主人公は、マンガ史のなかでも稀有なほど、痛快で愛くるしい、人の心に残り続ける素晴らしいキャラクターなのです。
きりとばらとほしと 後編
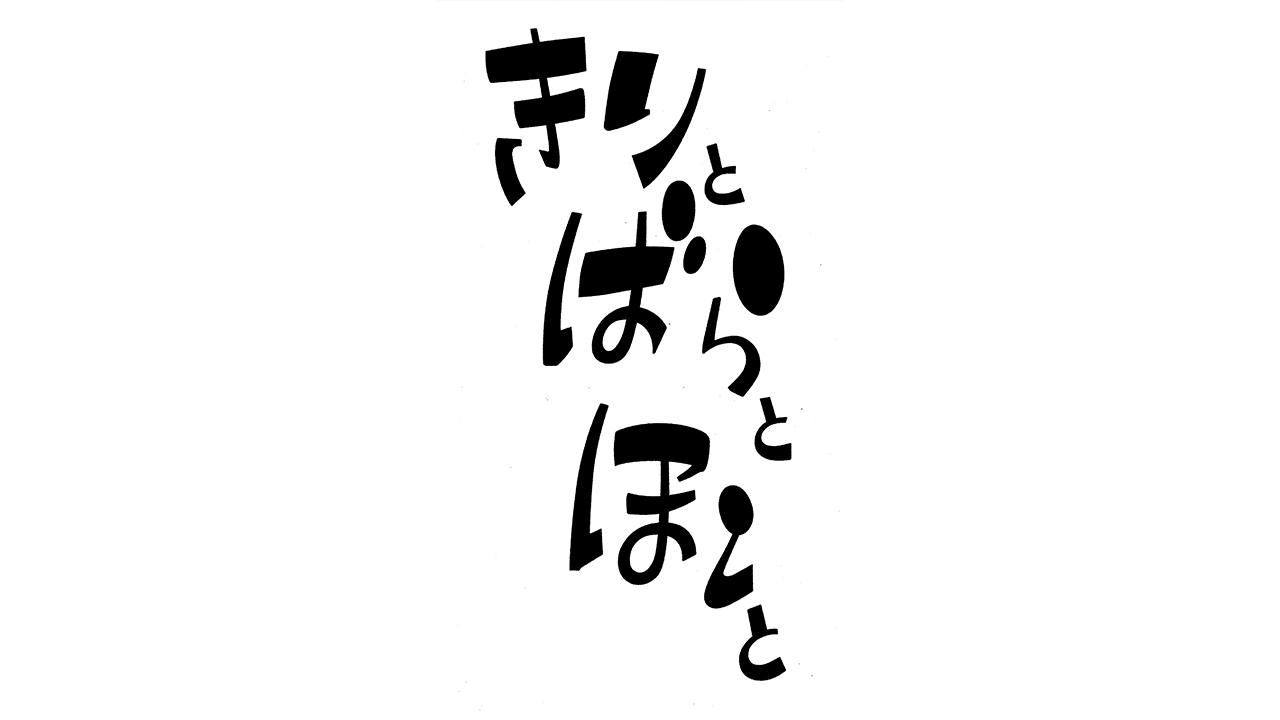
この作品は、過去(1903年)、現在(1962年)、未来(2008年)の三時代を生きる美しきバンパイアのリリーを描く、三部作。1962年当時、映画や小説などの世界ではオムニバス作品はあったかもしれませんが、マンガの世界ではどうだったのでしょうか?ちゃんと調べていないので、はっきりした事は言えませんが、当時ではかなり新しい試みだったのではないでしょうか。
きりとばらとほしと 前篇
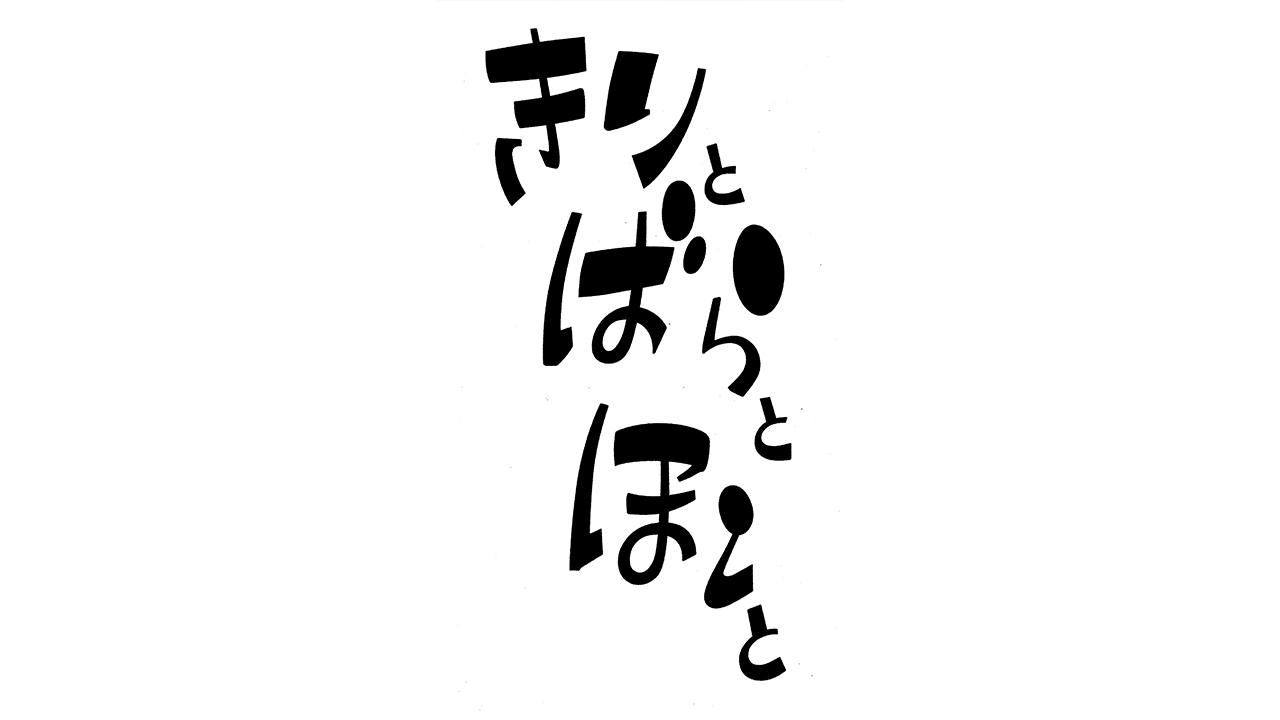
石森プロから「石森作品を追いながら、自分の感じたままのエッセーを連載しないか」と打診を受けまして、こうやって回を重ねておりますが、一つ一つ作品に触れていく事によって、僕が世界中のどの誰よりも尊敬してやまない石森と、こうして向き合える時間を頂けたようで、毎回とても嬉しく、ワクワクしながらキーボードを叩いております。