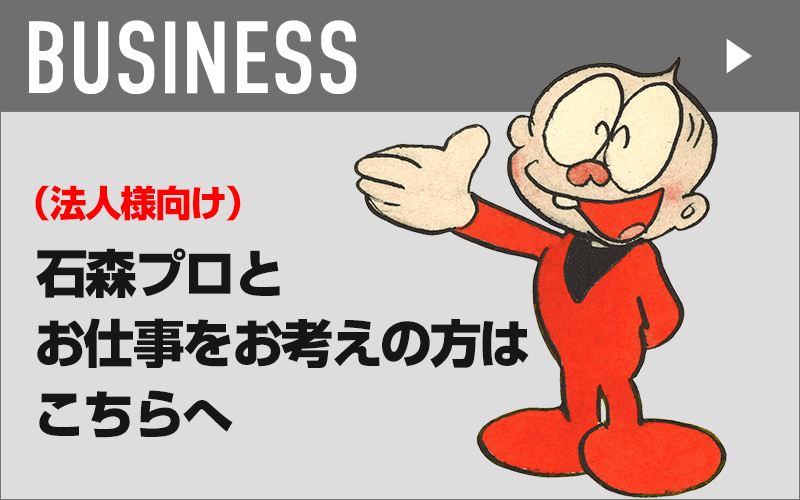石ノ森章太郎、本名 小野寺章太郎は、地方公務員ののち教育委員長にもなった父・康太郎、母・カシクの長男として、昭和13(1938)年1月25日に宮城県登米郡石森町(いしのもりちょう 現:登米市中田町石森)に生まれた。初期のペンネーム「石森章太郎」は、それで「いしのもりしょうたろう」と読んでもらえるはずだったが、誰も正しく読んでくれないまま「いしもりしょうたろう」となり、後年あらためて小さなノを入れて「石ノ森章太郎」を名乗った。
石森町は北側を岩手県と接し、近くには北上川が流れ、三陸の海からは30キロほど内陸の地。当時は住民の半数以上が稲作を主とする農業を営む小さな町だった。石ノ森章太郎の生家は現在でも残され、東京から新幹線で仙台駅よりも先の一ノ関駅まで進み、JR東北本線を戻るかたちで石越駅からバスで20分ほど揺られて向かう(見学可能)。すぐ近くに「石ノ森章太郎ふるさと記念館」が建ち、掌編『小川のメダカ』に描かれた幼いころののどかな風景が目に浮かぶ場所で、両親、姉、弟2人、妹、祖母、伯母と暮らした。小野寺家はもともと酒屋だったが、章太郎誕生時には味噌や醤油、塩、砂糖、切手やハガキといった“専売品”を含む雑貨屋を営んでいた。
出生当日の新聞は「ソ連國情實地踏査」の見出しで「關門ウラジオに上陸 對日祕密軍備を探る」と日本に忍び寄る戦争の気配を報じている。とはいえ、まだ時局は切迫するまでには至っていなかったのか、観劇の広告なども見られ、のんびりとした雰囲気も感じられる。同日、のちにマンガ家としてお互いしのぎを削りあうことになる松本零士氏も、本人曰く「東北と北九州の時差15分くらいでほぼ同時に」小倉の地に生まれる。この年4月に「国家総動員法」が交付され、日本は大きく戦争へとかじを切り、章太郎少年が石森小学校に入学した昭和20年の8月に終戦を迎えた。
「天気のいい日だった。近所の人たちが何人か集まってきてラジオの前に座っている(当時のこの辺のラジオの普及度はこんなものだった)。私は縁側に居た。大勢の人が集まっていることで何となく浮き浮きしていた。晴天、強い陽射し。縁の板が熱かった。ふと中を覗くと、みんなが泣いていた。びっくりした。明るい光に慣れていた眼は、部屋の中を薄暗く見せた。それが一層泣いている大人たちを異様なものにした。突然、私は笑い出した。何が何だか訳がわからなかったが、とにかくおかしかった。泣いている大人たちに声を聞かれないように、姿を見られないように扉の陰に蹲って、私はいつまでも笑い続けていた……。」(石ノ森章太郎「ことばの記憶」清流出版)
戦争は終わり、ようやく訪れた平穏な日々に、字を覚えた章太郎少年は読書に楽しみを見出した。幸いにも地域は空襲をまぬがれ、自宅も、父の蔵書も残されていた。あふれる知識欲で、夏目漱石、芥川龍之介、カントにショーペンハウエル…と、およそ手が届くすべての「文字」をむさぼり読み、そして…と、いかにも才気走った描写を目にすることも多いのだが、本質はそう単純ではない。章太郎少年がいかにして「天才」と称されるまでになったかの理由としては、さらに根底にある“闇”を見つめる必要があるだろう。
『ボクはダ・ヴィンチになりたかった』(清流出版)で語られている。あえて「書いておかねばならないだろう」と宣言をしてまで綴られた、幼き日に亡くしたすぐ下の弟・淳二への思いと引きずり続ける自責の念。上京するまで悩まされ続けた全身の湿疹には、半ズボンを履くこともためらうようになった。だからなるべく家にいて、同じく家にいることが多かった大好きな姉・由恵と遊ぶ少年時代を過ごした。
※敬称略